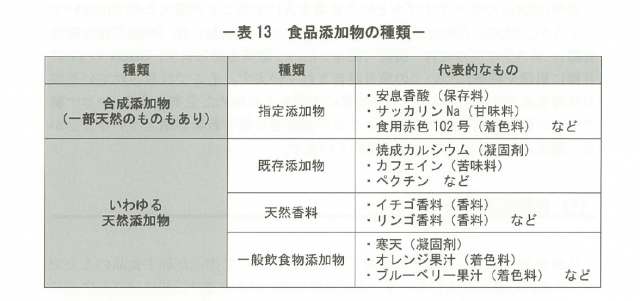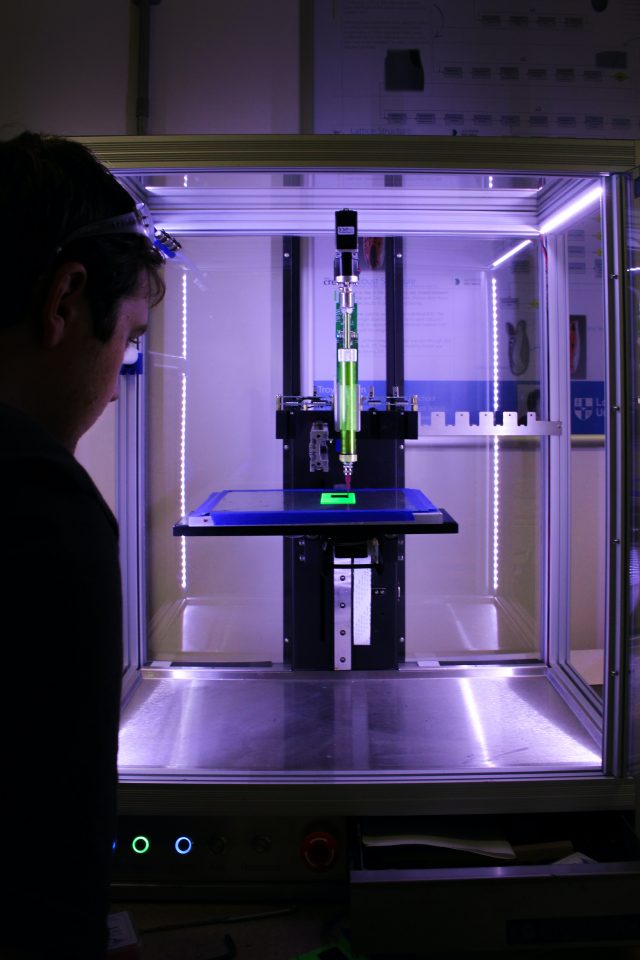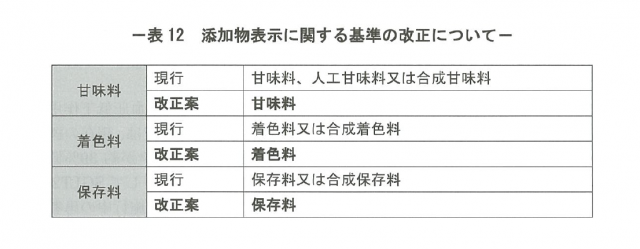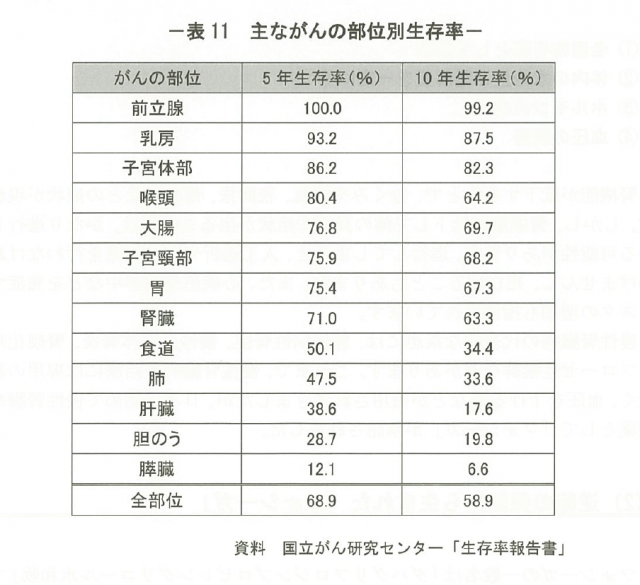2.代替食品の開発理由

〈環境〉
食生活にかかわる温室効果ガス(CO₂)の排出量は肉類の生産・出荷過程が最も多いといわれており、例えば、豚肉1kgを精肉するまでに排出されるの量は約7.8kgとされています。農林水産省によると、国民1人が1年間で消費する豚肉は約12kgと推定されているため、1年間で約93.6kgのCO₂排出量にもなります。この排出量をガソリンに換算すると(ガソリンは1ℓで約2.3kgのCO₂を排出)約40ℓを使用した場合と同じになります。他には、家畜を育てるための水や畜産業のための土地開発による森林伐採など、畜産業は環境への影響がとても大きいといわれています。
特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 185号」より抜粋