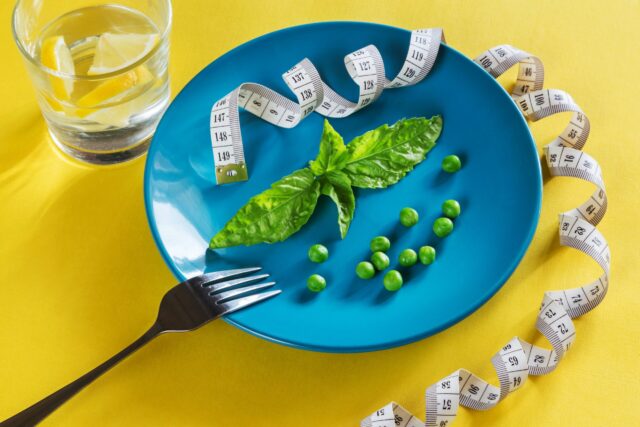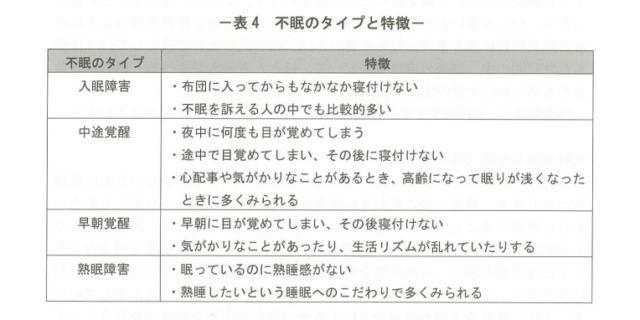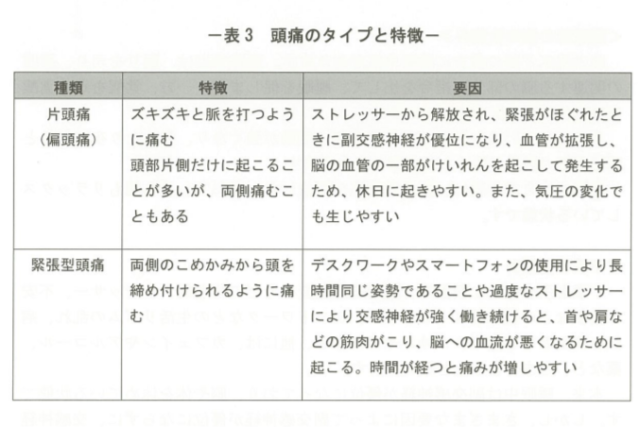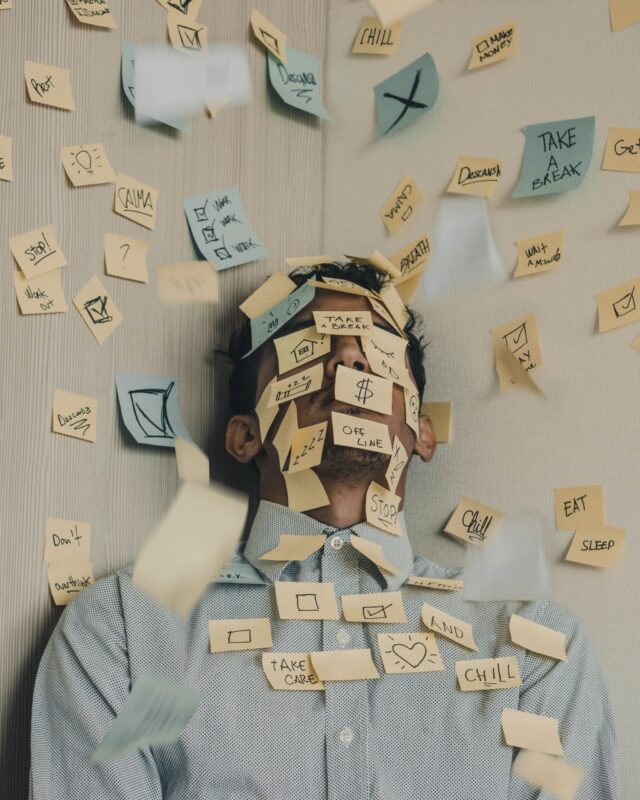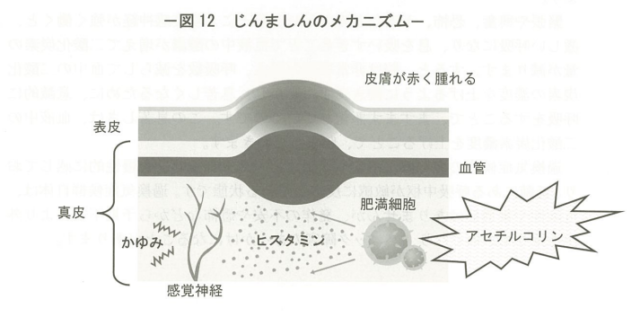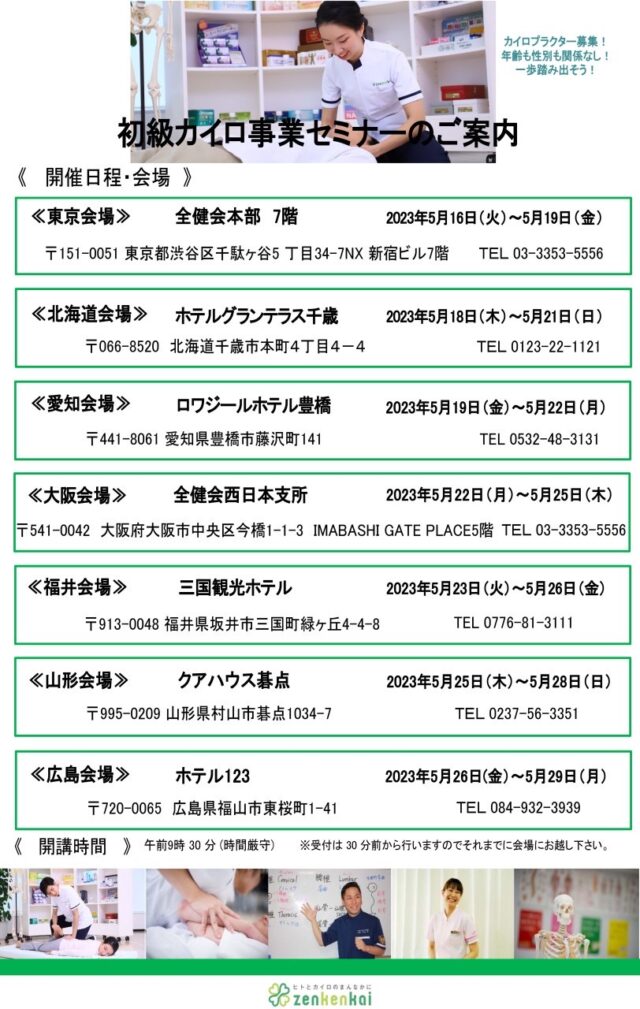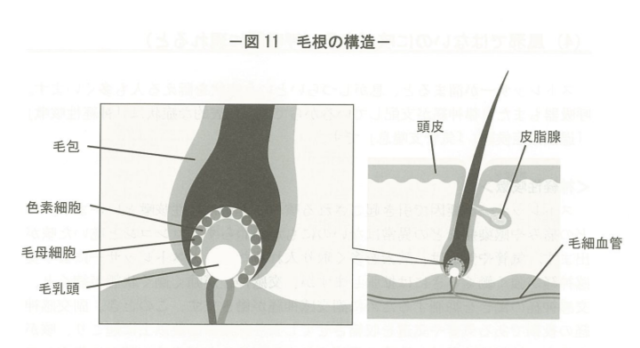2.自律神経のバランスが悪くなって現れる症状
(8)まぎらわしい症状に注意しよう!
自律神経失調症だと思っていたら、深刻な病気の初期症状だったということがあります。症状が軽いと受信せずに放置しがちですが、自己判断せずに体に異常を感じたときには、受診することがおすすめです。また、健康診断も定期的におこなうことがよいでしょう。
〈貧血〉
体のだるさ、動機、息切れ、頭痛、立ち眩みなどが自律神経の乱れで起こる不快症状と類似しています。赤血球のヘモグロビンに含まれる鉄が欠乏し、十分な酸素が送れなくなることでさまざまな症状を引き起こします。
〈糖尿病〉
のどの渇きや体のだるさ、多尿、食欲過多などが自律神経の乱れで起こる不快症状と類似しています。糖尿病でこれらの症状を自覚しているときには、既に進行しているじょうたいです。
〈甲状腺機能異常〉
発汗の異常、動機、体のだるさ、冷え、手足のしびれなどが自律神経の乱れで起こる不快症状と類似しています。更年期の女性に多く見られ、更年期障害にも間違われることがあります。
〈膠原病〉
発熱、体のだるさ、筋肉や関節の痛みなどが自律神経の乱れで起こる不快症状と類似しています。膠原病は、血管や皮膚、関節などで炎症が起こる自己免疫疾患です。要因がはっきりしていませんが、ストレッサーなどで悪化するといわれています。
特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 182号」より抜粋