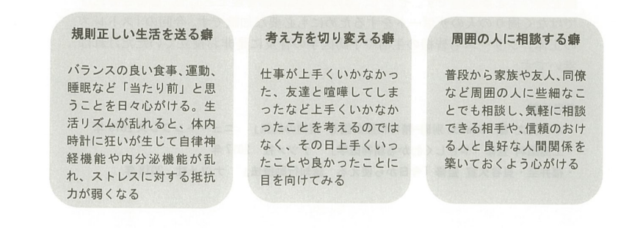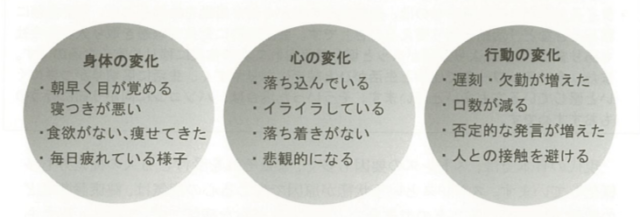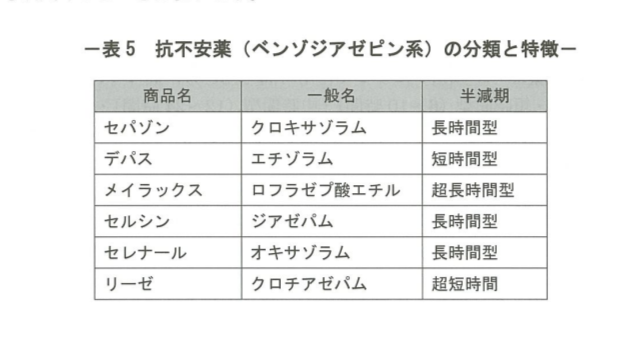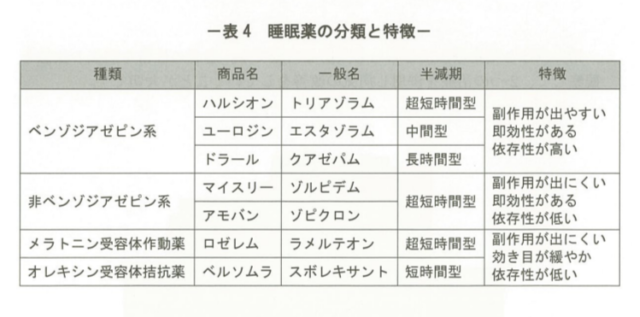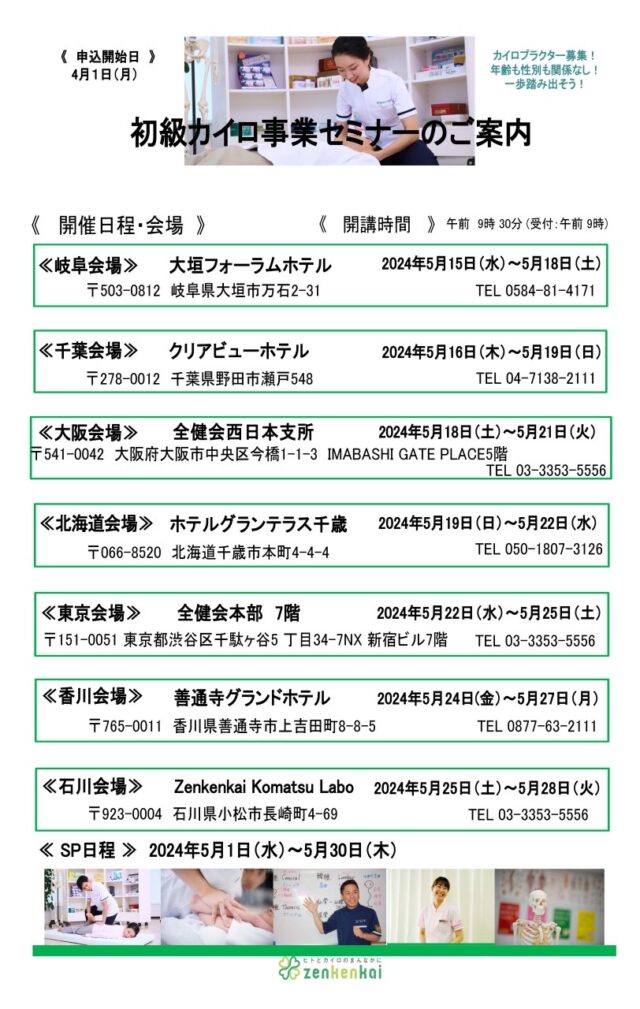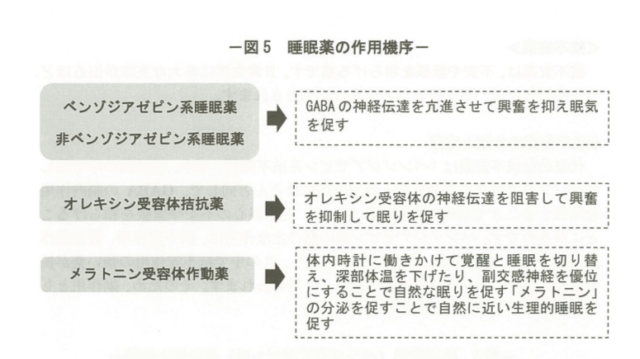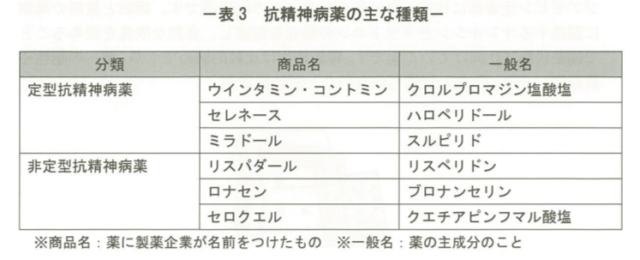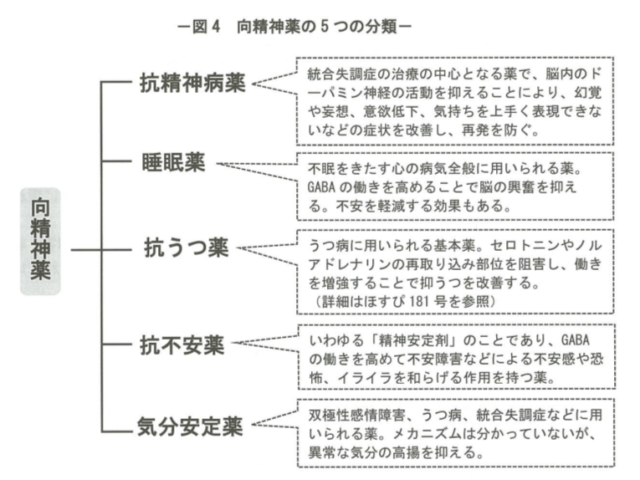1.アルツハイマー型認知症の新薬「レカネマブ」が誕生!
高齢化に伴い、認知症の患者数は増加傾向にあります。厚生労働省の調査によると、65歳以上の認知症高齢者は2025年に675万人(約5人に1人)と推定されています。認知症には、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症の4種類あります。中でも、アルツハイマー型認知症は認知症発症者の約6~7割を占めており、65歳以上で発症リスクが高まる傾向にあります。
*アルツハイマー型認知症とは(前編)
アルツハイマー型認知症は、脳内のアミロイドβと呼ばれる異常なタンパク質が蓄積して脳の神経細胞が死滅し、脳の萎縮が進行する認知症です。特に、記憶を司る海馬周辺から萎縮するため、記憶障害が現れます。症状の進行は比較的緩やかで、アミロイドβの蓄積は時間とともに増加するのが特徴です。また、症状が現れる数年~数十年前からアミロイドβの蓄積が考えられており、早期の治療。介入が重要視されています。
特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 発行「ほすぴ 197号」より抜粋